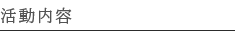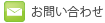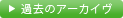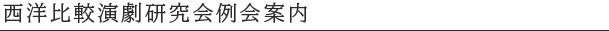
早いもので、今年度の例会のお知らせです。お忙しい折とは思いますが、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
※なお、最初の辻佐保子氏の発表は、質疑も含めて、英語のセッションとなります。
日時 2014年1月11日(土) 午後2時〜6時会場 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎2階大会議室http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html
■住所〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1
■交通アクセス
・日吉駅(東急東横線、東急目黒線/横浜市営地下鉄グリーンライン)隣接
※東急東横線の特急は日吉駅に停車しません。
〔研究発表1〕辻佐保子 ※英語セッション
(日)身体の現前性の称揚 - - ミュージカル『フェイド・アウト-フェイド・イン』における物語内容と形式の捻れに着目して
(英)The affirmation of physical presence - - an analysis of skew lines between the narrative and the form in Fade Out-Fade In
〔研究発表2〕村井華代
S.アンスキ『ディブック』とユダヤ演劇の近代
〔研究発表1〕<要旨>
本発表は1964年初演のミュージカル・コメディ『フェイド・アウト-フェイド・イン』の作品分析から、ミュージカル映画のバックステージを演劇として表す意義について論じるものである。ヒット作『ベルがなっている』(Bells Are Ringing, 1956) の制作者たち(脚本と歌詞:ベティ・コムデン&アドルフ・グリーン、作曲:ジュール・スタイン)が再結集し、主演を当時のTVスターであるキャロル・バーネットが務めたにも関わらず、『フェイド・アウト-フェイド・イン』はこれまで「スター主義的な作品群の一つ」及び「1930年代のミュージカル映画への諷刺」といった評価に留まり、詳細な研究はなされてこなかった。しかしながら、脚本家コムデン&グリーンの作風とも言われる形式やメディウムへの自己言及性に着目した時、ミュージカル映画の内幕を演劇として描くという本作に内包される捻れは看過しがたい。本発表では、これまで精密に論じられてこなかった作品の全体像を見直した上で、物語内容と形式との関わりを分析していく。そして、『フェイド・アウト-フェイド・イン』が映画の世界を取り上げることで逆説的に身体の現前性を前景化させ、演劇の特質として肯定しようとした作品であることを指摘して、再評価への端緒としたい。
〈プロフィール〉
辻佐保子
慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻卒業。早稲田大学文学研究科表象・メディア論コース博士後期課程在籍。アメリカン・ミュージカルにおける楽曲や歌うという行為の担う機能について、ベティ・コムデン&アドルフ・グリーン作品を中心に研究している。論文に「"Time is Precious Stuff" - - ミュージカル『オン・ザ・タウン』における時間表象についての考察」(2012年)、「電話・俳優・「パフォーマティブ」な演技のモード - - ミュージカル『ベルがなっている』論」(2012年)など。
〔研究発表2〕<要旨>
一般に、ユダヤ民族は偶像崇拝の禁止ゆえに、祭日行事であるプリム劇を除き、1870年代のイディッシュ演劇創始まで民族独自の演劇文化を形成してこなかったと言われる。そのような土壌に、19世紀末の4半世紀、2つのジャンルの演劇——ディアスポラ文化としての「イディッシュ語演劇」と、シオニズム運動の一環としての「ヘブライ語演劇」——が誕生したことについては、近代演劇全体の視野からもっと議論がなされてよい。この2種の近代演劇の在り方とその意味を、我々はどのように位置づければよいだろうか。
本発表では、その2ジャンル双方にとっての記念碑的作品である戯曲、S. アンスキ(S. An-sky, 1863−1920)の戯曲『ディブック——あるいは、ふたつの世界の間』を取り上げ、その複雑な成立の過程から、ユダヤ演劇の近代の一様相のあぶり出しを試みる。「ディブック」とは、ユダヤの伝承に登場する、生きた人間に憑依する汚れた魂をいう。アンスキは、1910年代の激動のロシアで、2年に渡るロシア帝国内の民俗学研究旅行を通じてこれを劇化、引き裂かれた恋人に憑依する青年の霊としてドラマ化した。「メロドラマ」と言われることも多いこの劇のモダニズムと、ユダヤ演劇の2ジャンルとの演劇の関係について、作者の人生の在り方と共に考察したい。
なお『ディブック』は、「エス・アンスキイ」作「デイブツキ」(中川龍一訳)として、『西班牙・猶太劇集』(『世界戯曲全集』第39巻「西班牙・猶太篇」、1930)邦訳刊行されている。
〈プロフィール〉
共立女子大学文芸学部教員。国別によらず、演劇現象学、反演劇主義とキリスト教神学等、西洋演劇理論を扱ってきたが、現在の主たる関心領域は、ユダヤ・イスラエル演劇。

年内最後の例会のご案内です。会場は今回は成城大学となります。
(なお、年明け最初の例会は1月11日慶應義塾大学日吉キャンパスで行います)
連続シンポジウム「スタニスラフスキーは死んだか?」第二回・日本におけるスタニフラフスキー
日時:12月7日(土)14:00-18:00
会場:成城大学 32H教室(正門から中庭に入って左の大きな建物3号館の2階。エレ
ベータ上がって、すぐななめ前)
※終了後同じ建物の1階の学生ホールの一隅で会費制の忘年会を開催予定です。
司会:井上優(明治大学)
講師:藤崎周平(日本大学)
講師:笹山敬輔(日本近代演劇研究)
「スタニスラフスキー・システムの歴史的検証」と題した第一回(2012年12月)は、浦雅春(東京大学大学院教授)・堀江新二(大阪大学大学院教授)両氏を講師にお呼びし、ロシアで誕生したスタニスラフスキー・システムとは本来どのようなものであったか、そしてロシアや海外で現在までどのように用いられてきた、ということについてお話しいただいた。その概要は電子ジャーナル『西洋比較演劇研究』第12巻第2号「例会報告」に詳しく収められている。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/12/2/12_297/_pdf
第二回「日本におけるスタニスラフスキー」は、藤崎周平(日本大学教授)・笹山敬輔(日本近代演劇研究)両氏をお迎えして、戦前から戦後にかけて日本でスタニスラフスキー・システムがどのように理解され、受容されてきたかについてお話しいただく。
1. 発表:笹山敬輔「戦前から戦後にかけてのスタニスラフスキーの受容」
演技術は、第一義的には演技をするための「技術」であるが、その背景には多様な思想や文化状況が存在している。そのため、スタニスラフスキー・システムのような西洋の演技術が日本に移入されるときには、その演技術が日本の身体観や心理観に影響を与えるとともに、それ自身も影響を受けて変容することになる。それは、受容者側の理解力不足の結果というよりも、その地域における文化状況との交渉であると言えるだろう。日本におけるスタニスラフスキーの受容を考えるためには、それぞれの時代の文化史研究・科学史研究とも接続しながら、脱領域的に論じていくことが必要となる。
本発表では、戦前から戦後にかけてのスタニスラフスキー受容について、三つの時期に分けて論じていく。最初が1910年代から1920年代で小山内薫を中心に、次が1930年代でプロレタリア演劇を中心に、最後が1940年代以降で千田是也の『近代俳優術』を中心とする。その際には、同時代の「身体」や「心」に対する認識の枠組みと照らし合わせながら論じていきたい。
発表者紹介
筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科文芸・言語専攻修了。博士(文学)。著書に『演技術の日本近代』(森話社、2012年)、「モンタージュ理論と演技術——村山知義の「新しい演技」」(岩本憲児編『村山知義 劇的尖端』森話社、2012年)。
2. 発表:藤崎周平「演技基礎教育におけるスタニスラフスキー的手法の実践−RelaxationとRepetition−」
スタニスラフスキー的手法が、日本の俳優養成の現場でどのように引用され、扱われているのか。特に、俳優の基礎教育における実践について報告したい。ここでいう“基礎教育”とは、実際の役作りの前に行われるものであり、演技を包括的に思考し、行っていくための根拠となりえるような訓練のことである。
今回紹介する2例は、1920年代以降、アメリカで展開したスタニスラフスキー・システムから引用された実践である。1つめは、前期の「感覚の記憶」から、リー・ストラスバーグが開発した《Relaxation》、さらには、いわゆるメソード演技が目指す“身体感覚を研ぎ澄ましていく”ために展開する一連の訓練であり、もう1つは、後期の「身体的行動」から、サンフォード・マイズナーが “相手との関係の中から自らの行動を発見していく”訓練として開発した、《Repetition》である。両者を検討しながら、システムの有効性について検討したい。
発表者紹介
日本大学芸術学部教員 専門は演技方法論及び俳優教育専門学科で俳優教育に20数年従事する。近著に『新演技の基礎のキソ』(主婦の友社)がある。

会場 明治大学駿河台キャンパス 研究棟4階 第一会議室
※校舎については以下をご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
※アクセスについては以下をご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
※リバティタワー正面より左手に研究棟への連絡通路があります。
シンポジウム「復讐の想像力に関する演劇の比較研究:セネカの戯曲と法思想をめぐって」
〈シンポジウムの趣旨〉
今回のシンポジウムは、2013年6月に日本演劇学会全国大会(於共立女子大学)で行われたシンポジウム「復讐の想像力に関する演劇の比較研究」の続編である。前回のシンポジウムでは古代ギリシャ、エリザベス朝、および16世紀後半のフランスの演劇に見られる復讐について検討した。今回はこれら三つの時代の復讐劇をつなぐ存在であり、西洋演劇における復讐の表象に大きな影響を与えたセネカの戯曲、ならびにその背後にあるローマの法思想について、二人の専門家に論じていただく。
シンポジウム・コーディネータ:小田中章浩(大阪市立大学)
〈コーディネータ・プロフィール〉
大阪市立大学大学院文学研究科教授。専門はフランス演劇、表象文化論。著作として『現代演劇の地層 —フランス不条理劇生成の基盤を探る』(ぺりかん社、2010年)および『フィクションの中の記憶喪失』(世界思想社、2013年)がある。
パネリスト1: 玉垣あゆ(名古屋大学)
〈発表要旨〉
セネカの悲劇は、後世の復讐悲劇に大きな影響を与えたと言われる。しかしラテン語において「復讐する」を意味する語ulciscor、u(v)indico、pu(oe)nioが、いずれも「罰する」という懲罰の意味を含んでいるように、彼の悲劇では「復讐(revenge)」と「罰(punishment)」が混在し、翻訳においても訳者の裁量に委ねられていると言える。発表では、劇中の言語に着目し、復讐、及び罰に係わる用語(特に「罰」と訳されることが多いpoena)の用法について詳細に見ていきたい。
〈発表者プロフィール〉
名古屋大学ほか非常勤講師。専門は西洋古典学(主にセネカ悲劇研究)。論文として「セネカの『オエディプス』における運命と意志」(『西洋古典研究会論集』21号、2012)「不実な夫の悲劇?セネカ『パエドラ』についての一解釈?」(比較文化研究106、2013)他がある。
パネリスト2: 林智良(大阪大学)
(1)まず、ごく簡単に法学とフィクション研究の関係を整理して自分の議論の出発点を定める。その際に、林田清明等によりつつ「法と文学」という研究潮流が法学に存在することに言及する。
(2)穗積陳重『復讐と法律』に専らよりつつ、現実の法思想・法制度が一般的には加害に対する報復の程度を制限しており、復讐の連鎖を続けさせない方向を目指したことを説明する。
(3)紀元前5世紀の十二表法における(加害への復仇の)同外報復への限定や元首政期(紀元後2世紀頃)の加害者委付制度などの説明を通じて、ローマ法が諸々の法体系の中でも特に復讐の制限に初期から積極的であったことを示す。その一方で、ユーゴスラヴィアのコソヴォ地方など、血讐を奨励する法体系も近代に至るまでヨーロッパにあった旨を(石部雅亮等によりつつ)示す。
(4)そのうえで、セネカの創造した劇世界に現実のローマ法思想・法制度が有した影響の可能性を、ギリシャ的素材に伏在するローマ的な地金を慎重に見分けつつ、見いだす。
〈発表者プロフィール〉
大阪大学大学院法学研究科教授(ローマ法専攻)。博士(法学)。1962年生まれ。京都大学法学部卒業・京都大学大学院法学研究科博士課程後期単位取得退学。主な著書として『共和政末期ローマの法学者と社会 -変容と胎動の世紀』(法律文化社、1997年)がある。

※なお、次回例会は11月23日(土・祝)明治大学を会場として行う予定です。
日時:10月5日(土) 14時〜18時
会場:慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎2階大会議室
■住所 〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1
■交通アクセス
・日吉駅(東急東横線、東急目黒線/横浜市営地下鉄グリーンライン)隣接
※東急東横線の特急は日吉駅に停車しません。
【研究発表1】
小山内薫の晩年における英雄・偉人劇について
—二世市川左団次の演じた『森有礼』、『戦艦三笠』、『ムツソリニ』を中心に— 熊谷知子
【研究発表2】
「全体演劇 わがジャンヌ、わがお七」の創造過程と上演の意味 佐野語郎
***************
概要
〔研究発表〕
小山内薫の晩年における英雄・偉人劇について
—二世市川左団次の演じた『森有礼』、『戦艦三笠』、『ムツソリニ』を中心に— 熊谷知子
〈要旨〉
本報告では、小山内薫(1881〜1928)作・演出、二世市川左団次(1880〜1940)主演による3つの作品、『森有礼』(1926年12月・歌舞伎座、翌年12月歌舞伎座で再演)、『戦艦三笠』(1927年11月・歌舞伎座)、『ムツソリニ』(1928年5月・明治座)の上演を中心に、小山内の晩年における商業演劇との関わりについて考えたい。小山内の晩年といえば、『国性爺合戦』など近松の改作やソ連訪問などがよく知られているが、まさにそれらと同時期の仕事である、上記の英雄・偉人劇の創作をはじめとした数々の商業演劇における仕事については、これまで十分な考察がされてこなかったように思う。たしかに、これらの戯曲は今日の読者の情動を揺さぶるものではない。しかし、上演時の劇評や雑誌の読者投稿を見てみると、当時流行していた伝記劇のなかでも決して評判の悪いものではなく、むしろ多くの観客を喜ばせていたであろうことが想像できる。今回は、この3つの英雄・偉人劇の上演を考察することで、小山内薫の商業演劇との関係について探る端緒としたい。
〈プロフィール〉
熊谷知子
慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻卒業。明治大学文学研究科演劇学専攻博士後期課程在籍。小山内薫の宗教信仰や商業演劇との関わりを中心に日本近代演劇を研究している。論文に、「「新劇場」と「至誠殿」—小山内薫の宗教信仰における一考察—」(『文学研究論集』37号、2012年)など。
〔研究発表〕
「全体演劇 わがジャンヌ、わがお七」の創造過程と上演の意味 佐野語郎
演劇ユニット 東京ドラマポケットvol.3+シアターΧ(カイ)提携公演「全体演劇 わがジャンヌ、わがお七」(作・演出:佐野語郎/2012年8月24日〜26日/東京・両国シアターΧ)の企画段階から上演終了までの創造過程を検証することで、企画の意図・脚本創作の動機・演出および演技などの実際を明らかにし、戯曲の再現・舞台化ではない演劇の自立性および上演における演技・音楽・舞踊・人形(お七とジャンヌ)などのポリフォニックな舞台表現(多声的要素)による全体演劇の可能性について考察したい。また、劇中劇(主人公は歴史上のヒロインではなく、その父と母)を展開させていくコロスたちは、ムーヴメント・合唱・語り・言葉の音楽・講談、そして劇中劇の人物としても加わりその演技の幅と多様性を求められたが、その演劇的存在についても考えたい。なお、この公演には、西洋比較演劇研究会の皆さんが何人も来場され、2013年1月発行の上演記念誌BOOKLETには五名の方が劇評を寄稿してくださっている。もちろん多くの会員の方は観劇されていないので、本報告では、資料DVD(34分・英文字幕入り)を映写することで、議論がさらに活発になればと願っている。この資料DVDは、公演完全収録版DVD(2時間15分)の映像記録も取り入れながら、まったく新たに公演紹介用として編集したものです。
〈プロフィール〉
佐野語郎
日本橋女学館高等学校非常勤講師。戯曲創作・舞台演出・童話出版の傍ら、高校・大学の演劇教育に携わる。全国研究集会における発表として「戯曲にみる聴覚効果と音楽演劇の多層性」(大手前大学)「演劇ユニットの形成過程と共同体としての特質」(大阪市立大学)ほか。

今回は会場を明治大学に移しての開催となります。
何卒奮ってご参集くださいますようお願い申し上げます。
2013年7月13日(土) 14時〜18時
会場 明治大学駿河台キャンパス 研究棟4階 第一会議室
※校舎については以下をご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
※アクセスについては以下をご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
※リバティタワー正面より左手に研究棟への連絡通路があります。
【研究発表1】
せりふと表情と翻案と —文士俳優・土肥春曙の理想と挫折— 村島彩加(明治大学)
【研究発表2】
セネカ悲劇に見る「運命」と「人」〜『トロイアの女たち』における劇構造の観点から〜
玉垣あゆ(名古屋大学)
※終了後臨時総会が開催される可能性があります(15分程度の予定)。
***************
概要
【発表要旨1】
せりふと表情と翻案と —文士俳優・土肥春曙の理想と挫折— 村島彩加
文芸協会の俳優として演劇史に名を留めている土肥春曙(1869〜1915)は、従来の演劇研究において言及されることの少ない存在であった。その当たり役としては、文芸協会公演における『ハムレット』のタイトルロールが知られているが、彼の役者としてのスタートは明治38年(1905)であり、その活動は短い一生の最晩年の10年に満たない。しかし、彼は明治34〜35年(1901〜02)の川上音二郎一座欧州巡業に「通訳兼演劇研究」として随行して以降、多くの演劇および文芸雑誌に欧州の演劇事情を紹介する文章を掲載、また従来の歌舞伎とも新演劇とも違う新しい演技の創生を提唱し、社会劇の翻案上演を推奨していた。それらの言説、またそこに立脚しての彼の演劇活動からは、彼が文芸協会の花形役者としてだけではなく、様々な角度から時代に即した新しい演技を模索していた過程が浮かび上がってくる。本報告では、従来等閑視されがちであった春曙の活動を「俳優として」「文士として」「演劇の指導者として」の三点から検証し、彼が理想とした新しい演技と、その完成に向けての模索の跡を辿ることで、初期の新劇における演技術創出の一端を知ることを目的としたい。
<発表者プロフィール>
村島 彩加
明治大学文学部兼任講師。幕末〜大正期の演劇写真に見る歌舞伎の近代化を検証することを中心に、化粧、表情など演技の様々な要素の近代化を研究している。
【発表要旨2】
セネカ悲劇に見る「運命」と「人」〜『トロイアの女たち』における劇構造の観点から〜
玉垣あゆ(名古屋大学)
昨年末イスラエルに於いて、エウリピデス作『トロイアの女たち』がアラブ系、ユダヤ系のイスラエル人と日本人の俳優たちによって上演されたことは記憶に新しい。前416年のアテーナイ人によるメーロス島民虐殺事件を踏まえて作られたこの劇は、一般に「反戦劇」と解釈される。それに対し、エウリピデスから約450年後、平和を謳歌する古代ローマにおいて、哲学者セネカによって制作された同名の悲劇は、トロイア戦争後のトロイアという舞台背景、敗者であるトロイアの女たちと勝者であるギリシアの将軍たちという登場人物たちこそほぼ同一であるものの、「反戦劇」と捉えられることはない。これは、劇中に冥界の描写や亡霊の登場が認められる一方、「死後は何も存在しない」というストア思想を歌う第二合唱歌の存在があり、この矛盾をどう解釈するのか、「死」について多く論じられてきたためである。しかしこの部分的な矛盾に捕らわれるあまり、先行研究では全編を通した劇そのものの解釈が疎かにされてきたように発表者には思われる。本発表では、『トロイアの女たち』におけるセネカの独自性を確認した上で、「輪の構成(ring-composition)」と登場人物たちの対応関係という既に指摘された劇構造に再度着目し、登場人物たちの間に新たな対応関係を見出すことによって、「運命」という枠の中で人がいかに生きるか、人としての心のあり方が本作品を通して読みとられることを明らかにしたい。
〈発表者プロフィール〉
玉垣あゆ
名古屋大学ほか非常勤講師。専門は西洋古典学(主にセネカ悲劇研究)。
「セネカの『オエディプス』における運命と意志」(『西洋古典研究会論集』21号、2012)
「不実な夫の悲劇−セネカ『パエドラ』についての一解釈−」(比較文化研究106、2013)

※同著書の購入を希望される方は、先日のメールをご参照ください。
日時 5月18日(土) 14:00〜18:00
場所 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎一階シンポジウムスペース
※予約名は「慶應演劇論研究会・西洋比較演劇研究会」となっています
※交通アクセスは以下を参照(地図の9番の建物です)
http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html
新刊書評討論
エリカ・フィッシャー=リヒテ『演劇学へのいざない 研究の基礎』山下純照、石田雄一、高橋慎也、新沼智之訳、国書刊行会、2013年4月
参加者:訳者;石田雄一(中央大学)、高橋慎也(中央大学)、新沼智之(明治大学)
質問者;中島裕昭(東京学芸大学)、萩原健(明治大学)
※山下純照氏は在外研究で日本におられないため参加できません。
まずは訳者に本書の内容を簡単に説明してもらい、続いて、同著者の『パフォーマンスの美学』を翻訳した質問者のお二人から口火を切っていただき、それからフロア全体で討論をするという進行を予定しています。
ドイツ語からの訳書ですので、もちろん討論が翻訳の問題に及ぶこともあるかとは思いますが、基本的には日本語レベルでの討論を、と考えております。時間もたっぷり確保しておりますので、内容の不鮮明なところの確認なども含めて、多くの質問、意見、感想が出てくることを期待しております。
《討論参加者・質問者プロフィール》
石田雄一
中央大学法学部教授。ドイツ演劇・文学。「演劇が聞こえる風景—ハイナー・ミュラーの『絵の記述』と『ヴォロコラムスク幹線路』を例に」(『近代劇の変貌』中央大学出版部、2001年所収)、「祭儀の物語性と劇性について—カロリング朝時代のミサの変化を例に」(『「語り」の諸相』中央大学出版会、2009年所収)。
高橋慎也
中央大学文学部ドイツ語文学文化専攻教授。ドイツ演劇・文学。「マルターラー演劇の「孤独」のモチーフとパフォーマンス性 : 演劇ドキュメンタリー映画『家族会議(Familientreffen)』を題材として」(中央大学ドイツ学会『ドイツ文化』67、2012年)、『テロリズムの記憶と映像芸術』(日本ドイツ学会紀要42、2008年)、『ドイツ統一後のベルリン演劇の展開』(中央大学文学部紀要100、2007年)など。
新沼智之
明治大学ほか非常勤講師。演劇学、ドイツ演劇の近代化プロセス。「ドイツ演劇の近代化の出発点—コンラート・エクホーフの試行錯誤」(『演劇の課題』三恵社、2011年所収)、「18世紀後半のドイツにおけるアンサンブル演技理念の方がと劇団規則」『西洋比較演劇研究』第12巻2号、2013)など。
中島裕昭
東京学芸大学演劇分野教授、学部表現コミュニケーション専攻・大学院表現教育コース担当。専門は現代ドイツ演劇・文学、演劇教育、パフォーマンス研究。共著に『ドラマ教育入門』、共訳に『パフォーマンスの美学』など。
萩原 健
明治大学国際日本学部准教授。現代ドイツの舞台芸術(特に演出の歴史)および関連する日本の舞台芸術。共著に『村山知義 劇的尖端』、共訳に『パフォーマンスの美学』など。舞台通訳、字幕翻訳・制作・操作。

新たな年度の開始となりました。
先日お知らせしたように、以下のように総会と最初の例会をひらきます。
懇親会も行いますのでぜひご参加ください。
日時 2013年4月13日(土)14:00~18:00
場所 成城大学7号館3F 733教室
1 総会
2 研究発表 日比野啓氏(成蹊大学)
【研究発表要旨】
管理された無秩序:「バナ学バトル★☆熱血スポ魂秋の大運動会!!!!!」における身体と「なりきり文化」
日比野啓(成蹊大学)
アニメの主題歌やアイドルの楽曲を中心としたJポップをサンプリングして大音響で流しながら、制服・軍服姿の男女が踊り、叫び、舞台から客席に向かってなだれ込み、物や液体を投げつける、というバナナ学園純情乙女組(以降「バナ学」)の挑発的で刺激的な公演は、1980年代以降の小劇場演劇とは一線を画し、精神においてアングラ演劇を思い起こさせるものであり、とりわけ観客とのインタラクションに重きをおくそのスタイルは近年の日本の小劇場におけるコミュニケーションのありようを再定義するものであった。その一方で、アングラの実践を理論的に補強するものだった、疎外論にもとづく解放言説?「肉体の叛乱」(土方巽)という言葉が想起させるような?とバナ学は無縁である。バナ学のパフォーマンスが作り出すカオスとは、あらかじめその効果を厳密に計算された、管理されたものであり、パフォーマーたちが振り付けどおりの一糸乱れぬ動きをするさまは北朝鮮のマスゲームまたはナチスドイツ時代の軍隊行進を思わせるものだからだ。にもかかわらず、竹内敏晴ならば「学校的身体」と呼んだかもしれないバナ学のパフォーマーたちの身体は生き生きと躍動しており、生のエネルギーとしか呼びようのないものが劇場には充満している。本発表では、バナ学のこれまでの作品をビデオで紹介しながら、同時代サブカルチャーとの密接な関係、とりわけカラオケ/コスプレ/ニコニコ動画「やってみた」といった、日本的な「なりきり文化」の影響を確認したうえで、これを補助線として、抑圧/解放という二項対立を無効化する新たな身体論の実践としてバナ学の公演を位置づけたい。
日比野啓。成蹊大学准教授。東京大学大学院文学部英文科修士課程、ニューヨーク市立大学演劇学科博士課程修了。編著に『明治・大正・昭和の大衆文化─「伝統の再創造」はいかにおこなわれたか』(彩流社、2008年)など、共著に松本尚久編『落語を聴かなくても人生は生きられる』(ちくま文庫・2012年)など。論文に "Oscillating Between Fakery and Authenticity: Hirata Oriza's Android Theatre" (Comparative Theatre Review, 11:1 [2012]) など。
*例会終了後、2013年度の懇親会をおこないます。

大変、恐縮ですが、発表者の1人であるフランセス・コーザ氏より、感染性の高い病気に罹ったため、残念ながら発表をキャンセルしたい旨の連絡が入りました。 運営委員会としては、やむを得ないこととし、急遽、発表者と発表内容(および再度、開始時間を)次のように差し変えて実施することにいたしました。
度重なる変更で、皆様にご迷惑をおかけすることをお詫びするとともに、ご理解のほどよろくお願いする次第です。
期日 2013年1月26日(土)午後2時から
会場 成城大学7号館2F 723教室
「ハインリッヒ・フォン・クライストの喜劇『壊れ甕』の隠されたモデル
― 「ルンポルトとマレート」を主人公とする謝肉祭劇との関連性 ― 」
要旨
『壊れ甕』(1806年完成、1811年初版)の創作については、作者自身が“zusammengesetzt“「取り合わせて作った」という形容をしている。クライスト研究者ゼンプトナーは、そのことに触れつつ、作者が『壊れ甕』を「取り合わせて作った」際の源泉という意味で、同作とラーベナーの『諷刺的書簡集』との関連性を初めて指摘した(このことは近藤公一によって我が国でも紹介されている)。
本発表は、『壊れ甕』のそのような源泉の一つとして、15世紀末から16世紀初頭に書かれたと推定されている“Rumpolt und Mareth“「ルンポルトとマレート」を主人公とする謝肉祭劇(以下RMSと略す)をも加えるべきである、という主張を掲げ、これを論証することを目的とする。
『壊れ甕』とRMSとの関連性については1923年に書かれたカール・ホルの『ドイツ喜劇史』の中で既に言及されている。しかし、ホルの本は長い期間にわたるドイツ喜劇史の概観であるため、個々の作品についての詳しい分析は行なっていないし、『壊れ甕』とRMSとの間テクスト性についての分析もなく、従って間テクスト性は、ホルの本では直感的な理解にとどまっている。しかもその後のクライスト研究史において、このホルの見解は、管見の限り、忘れられてきた。
発表の段取りは以下の通りである。まず、研究の中で『壊れ甕』の源泉として既に認定されてきた諸要素の整理を行う。これらの源泉群は、2つに分かれる。一種の裁判劇であり、その上で喜劇であり、さらに裁判官アーダムの転落だけをテーマとして持つのではなく、若い男女の婚約とそれに関するトラブルと解決をも重要なテーマとして持っている『壊れ甕』にとって、モデル性が強いと言える源泉(『旧約聖書』、ソフォクレスの『オイディプス王』、ドビュクールの油彩原作によるル・ヴォーの版画『壊れ甕』)と、モデル性が限定的または存在しない源泉(『新約聖書』、ラーベナーの『諷刺的書簡集』、ことわざ「甕も壊れるまでの水場通い」、近世オランダ史の知識、裁判ないし裁判史についての知識)である。
次いで、RMSが、人物構成、主要な2人の登場人物の名称と性格、そして主題という3つの点で『壊れ甕』と強い類似性をもっていることを示す。劇の構造の点ではRMSは恐らく『壊れ甕』のモデルになっていない(その点ではむしろ『オイディプス王』が手本となっている)。ただ、個々の台詞のレヴェルでも、『壊れ甕』とRMSは目立った類似性をいくつも示している。
クライストはRMSをモデルとして彼の喜劇を創作するに当たって、いくつかの「ひねり」と「反転」を加え、この謝肉祭を、いわば隠し絵のごとき下敷きとして利用したと思われるのである。
<プロフィール> やました・よしてる 成城大学文芸学部教授。専門はドイツ近・現代演劇、演劇理論。研究テーマは「演劇と記憶」。論文に「ジョージ・タボリ『記念日』の創作過程にみるユダヤ的アイデンティティーの構築 ― 最終場の決定と解釈をめぐって ― 」(『演劇学論集 日本演劇学会紀要45』2007年)、「野田秀樹の『ザ・ダイバー』における「演劇の修辞学」 ― 能『海士』との関係生 ― 」(大阪大学演劇学研究室編『演劇学論叢』11、2010年)。
---
2 岡本光代(研究発表) 「大正期新舞踊運動における一考察」
大正時代の日本演劇を彩る一つの活動に新舞踊運動がある。明治37年坪内逍遙の『新楽劇論』および『新曲浦島』に端を発するこの運動は舞踊家のみならず歌舞伎俳優にも広まった。そのきっかけとなったのは二代目市川猿之助(のちの初代市川猿翁)の活動である。大正8年、半年にわたる洋行を終えて発表した『すみだ川』を皮切りに、猿之助は自身の研究団体春秋座において『蟲』などの多くの舞踊作品を発表した。そしてこのような活動に影響された多くの歌舞伎俳優がさまざまな作品を作ったことで大きな流行を見せたのである。しかし、現在ではこの時期の新舞踊運動について、またその運動がも
たらしたものに触れられることはあまりないといってよいのではないだろうか。
本報告においては、二代目市川猿之助を中心とした歌舞伎俳優による新舞踊運動を、具体的にどういう上演であったのか、舞踊の内容だけではなく舞台装置や照明といった点からも検討する。そして大正期の新舞踊運動の活動、その意義、現在までの影響について考察することを目的としている。
<プロフィール>:明治大学大学院文学研究科演劇学専攻所属。研究テーマは日本演劇の近代化であり、主に大正時代の日本演劇を研究の対象としている。既発表論文に「屋根と夕日、そして狂人―十三代目守田勘弥による『屋上の狂人』上演試論」(『文学研究論集第36号』、2011)などがある。

連続シンポジウム「スタニスラフスキーは死んだか?」
第一回・スタニフラフスキー・システムの歴史的検証
日時:2012年12月15日(土)14:00~18:00
会場:成城大学7号館3階732教室
司会・問題提起:井上優(明治大学准教授)
講師:浦雅春(東京大学大学院教授)
講師:堀江新二(大阪大学大学院教授)
俳優は内面で実際に感じる感情をもとに演技しなければならないという主張は、ドゥニ・ディドロ「俳優に関する逆説」(1758)をはじめとしてたびたび批判されてきたにもかかわらず、今でも多くの国の演劇・映画における演技術の土台として受け入れられている。一方、20世紀初頭のロシアにおいて誕生したスタニフラフスキー・システムは、俳優の「役作り」の方法論を体系化することで、演技=俳優の内面という言説の有効性を確証したと考えられているが、現在演劇研究の場だけでなく、演劇教育および実践の場においても顧みられることはあまりにも少ない。スタニフラフスキー・システムは本当に「死んだ」のだろうか? 2012年末から2013年にかけて、日本演劇学会分科会・西洋比較演劇研究会ではスタニフラフスキー・システムの可能性と限界について研究者や実践家が熱く語る連続シンポジウムを開催する。
第一回:スタニフラフスキー・システムの歴史的検証
第二回:日本におけるスタニフラフスキー・システムの展開とその可能性
第三回:スタニフラフスキー・システムの「超克」
記念すべき第一回はスタニフラフスキー『俳優の仕事』をロシア語版から完訳した共訳者である浦雅春・堀江新二両氏を迎えて、スタニフラフスキー・システム成立の歴史的経緯を考察する。
会員以外の参加を歓迎します。参加費等不要ですが、会場整理の都合上、参加ご希望のかたは前日までにメール(constantin@comparativetheatre.org)または電話050-5809-5459(留守電が対応します)でご連絡ください。*会員各位:例会後、2012年度の懇親会を行います。
問題提起:井上優「さまざまなスタニスラフスキー」
スタニスラフスキーは単一ではない。スタニスラフスキー自身の中でシステムに関する考え方が変化しているからあるのは言うまでもなく、それを受容する国や地域の事情によっても、システムは(恣意的であるにせよ無意識であるにせよ)修正され改変されている。
結果として、スタニスラフスキーの継承者を自負する(あるいは周囲にそうみなされている)者たちによって、「さまざまなスタニスラフスキー」の乱立が引き起こされることになる。
たとえば、有名な話だが、コミサルジェフスキーは彼自身モスクワ芸術座に一度もいたことはないにもかかわらず、フランスやイギリスではスタニスラフスキーの継承者であるかのように扱われる。アメリカのメソッド・アクティングにおいても、指導者たちが互いを批判しつつ、それぞれがスタニスラフスキー・システムの継承者であることを主張している。
それは、もちろん、歴史的過去の出来事であるばかりではなく、現在形の現象ともいえる。それを批判しても益はないだろうが、少なくとも、その事実を認識したうえで、そうした複数形のスタニスラフスキーを、「それでもスタニスラフスキーである」のか「もはやスタニスラフスキーではない」のか、あるいは、その観点からの検証が可能なのか、不可能なのか、というような問いかけを行うことは意義があるだろう。その観点から、いくつかの事例を引用しつつ、シンポジウム全体への司会者からの問題提起としたい。
発表者紹介
明治大学准教授。専攻は演劇史・演劇理論全般。最近の論文に「今なぜ岩田豊男なのか—岩田豊男の演劇論を読む」(『演劇の課題』三恵社)、「一心太助は朝日を背に日本橋を渡る —『家光と彦左と一心太助』 (1961)の背景にあるもの」(『日本橋学研究』第五号)他。
--------------
2. 発表:浦雅春「スタニスラフスキーかメイエルホリドか」
20世紀の演劇は2つパラダイムを軸に展開してきた。ひとつはスタニスラフスキーが作り上げた俳優術、いわゆるスタニスラフスキー・システム、もうひとつはメイエルホリドの編み出した身体操作術である。スタニスラフスキーが人間の心理・感情を掘り下げ、舞台上で「生きる」には役者にどのような手立てがあるのかを探求し、そこから「サイコテフニカ」という技術を生み出したとすれば、メイエルホリドは心理と感情を排除した身体に演劇の可能性を拓く「ビオメハニカ」を提唱した。
もともと芸術座でスタニスラフスキーの弟子であったメイエルホリドが、芸術座の演技のあり方を自然主義、たんなる現実の忠実なコピーにすぎないと痛烈に批判し、それに対抗するものとしてコンヴェンションに基づく「制約劇」という概念を打ち出したことから、このふたつのパラダイムはとかく対立的にとらえられてきた。精神—身体、生—機械、真実—約束事という二分法のなかにあって、つねにスタニスラフスキーは前者に位置づけられ、メイエルホリドは後者に括られてきた。「真実らしさ」や「人間の精神」といった、いささかいかがわしい用語を駆使するスタニスラフスキーは旧弊で保守的に映り、心理や情緒とはすっぱり縁を切ったメイエルホリドの演劇は「革新的」だと思われてきた。たしかに論点を明確にするためには、このような単純な二分法も有効であるにはちがいないが、この図式からこぼれ落ちるものも多い。いまこそ問われるべきは、はたしてスタニスラフスキーはそれほど心理主義に傾いていたかという問いであろう。
発表者紹介
東京大学大学院教授。著書に『チェーホフ』(岩波新書、2004年)、訳書にチェーホフ『桜の園/プロポーズ/熊』(光文社古典新訳文庫、2012年)、ブローン『メイエルホリド 演劇の革命』(水声社、2008年、共訳)、スタニスラフスキー『俳優の仕事』全3巻(未来社、2008年、共訳)他。
--------------
3. 発表:堀江新二「等身大のスタニスラフスキー—USバイアス・USSRバイアスを超えて」
スタニスラフスキーは、その演技術を俳優学校の授業として確立しているが、それは40年近い紆余曲折の実験の日誌である。その一部を肥大化して取り出すと、様々なバイアスがかかってしまうが、その実態をロシアとアメリカの俳優教育を例に考えてみたい。そのために、まずモスクワ芸術座でのチェーホフ演劇以降、1938年に亡くなるまで、演技論や俳優教育の考え方にどのような変化があったのか、いくつかの例を取り上げて、スタニスラフスキーの心身論の実態に迫ろうと思う。そして、実際の俳優教育の現場での経験(モスクワ・シューキン演劇大学とアメリカ・イエール大学などでの)を通し
て、いわゆるスタニスラフスキー・システムの受容のあり方を考える。その際、ロシアでもアメリカでも話題になったオイゲン・ヘリゲルの『禅と弓道』の意味を、ミハイル・チェーホフの演技術・演劇観の日本語への全訳を視野に入れて、触れてみたい。俳優教育自体が軽視されている日本で果たして、こういったことがどのような意味を持つのか、問いかけつつ…
発表者紹介
大阪大学大学院教授。新劇女優だった母の影響で、5歳から60年間俳優の演技を見てきた。ロシアで本物の俳優に出会えたことが、無上の喜びだが、日本に帰ると絶望感に。2006年、58歳でシューキン演劇大学俳優学科に「特別」入学。著書に『したたかなロシア演劇』(世界思想社、1999年)他。訳書にスタニスラフスキー『俳優の仕事』全3巻(未来社、2008年、共訳)他。

シンポジウム「18世紀ヨーロッパにおける演技の諸相」
日時:2012年10月13日(土)14:00~18:00
会場:成城大学 7号館 731教室
司会 安田比呂志
発表
奥香織「18世紀フランス演劇とイタリア人劇団――演劇創造の源としての演技」
大崎さやの「リッコボーニ親子の演技論について~イタリアにおける演技論の系譜」
菊地浩平「サミュエル・フットのふたつの演劇論」
新沼智之「一八世紀ドイツにおける演技理念の大転換 ― アンサンブル演技の萌芽」
発表要旨およびプロフィール:
奥香織「18世紀フランス演劇とイタリア人劇団――演劇創造の源としての演技」
【発表要旨】
旧イタリア人劇団の国外追放(1697)以降、パリでは長らくフランス人劇団(コメディ=フランセーズ)が特権的地位を独占する状況が続いたが、1716年に新たな劇団が来仏すると両劇団が競合する状況となる。イタリア人劇団はパリに定住して活動する中で「フランス化」し、即興性や身体性は次第に影を潜めていくが、それでもなお役柄は類型化し、特にアルルカン役者トマサンと女優シルヴィアの「ナイーヴ」な演技によって観客を魅了した。また、彼らの演技はフランス人作家を惹きつけ、マリヴォーなど世紀前半を代表する作家の作劇法にも影響を与えた。当時の「フランス式」演技からすればイタリア人俳優の演技は異質であったが、俳優と役柄が一体化し、躍動感があるだけでなくまとまりのある舞台を作り出す彼らの演技は、作家の創作活動における想像力の源となっていたのである。7月の発表では、強調性、身体性、役柄との一体化という点からイタリア人劇団の演技を考察したが、本発表では、前回の発表と議論の内容をふまえ、特にトマサンとシルヴィアの演技に光を当て、フランス人俳優との比較も行いながら、イタリア人劇団の演技方法に関する考察を深める。また、彼らの演技が当時の劇作家に与えた影響を検討することで、18世紀フランス演劇における同劇団とその演技の重要性を明らかにする。
【プロフィール】
早稲田大学ほか非常勤講師、早稲田大学演劇博物館招聘研究員。専門はマリヴォーを中心とする18世紀フランス演劇、日仏演劇交流史。主要論文に« L’idee de ‘‘jeu’’ dans Le Petit-maître corrige de Marivaux »(『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』19号、2010年)など。
大崎さやの「リッコボーニ親子の演技論について~イタリアにおける演技論の系譜」
【発表要旨】
18世紀に活躍したルイージ・リッコボーニ(Luigi Riccoboni)はコンメディア・デッラルテの俳優であり、劇団の座長であり、さらに演劇理論家でもあった。彼の演技論『演技術について “Dell’arte rappresentativa”, 1728』および『朗誦術に関する論考 ”Pensees sur la declamation”, 1738』と、彼の息子でやはりコンメディア・デッラルテの俳優だったフランチェスコ・リッコボーニ(Francesco Riccoboni)の『演技術“L’Art du theatre”, 1750』を、レオーネ・デ・ソンミ(Leone de’ Sommi)やピエトロ・マリア・チェッキーニ(Pietro Maria Cecchini)を始めとする、ルイージやフランチェスコ同様の演技の実践者によって書かれた、過去のイタリアにおける演技論と比較しながら、その革新性を検証する。同時に、当時のヨーロッパにおける演技論の潮流と比較しながら、西洋演劇史における二人の演技論の持つ意義を再検討したい。
【プロフィール】
東京大学大学院にて博士(文学)。専門は18世紀イタリア演劇。著書『イタリアのオペラと歌曲を知る12章』(共著、2009年、東京堂出版)他。現在東京大学他にて非常勤講師。
菊地浩平「サミュエル・フットのふたつの演劇論」
【発表要旨】
サミュエル・フットは、1747年に『情念に関する論文』と『イギリス及びローマ喜劇の考察と比較』という2本の演劇論を発表し、のちに名を成すこととなる喜劇作家としてよりも先に演劇理論家としてのデビューを果たしている。ただ『情念に関する論文』は、18世紀英国演劇に彩りを添えていたデイヴィッド・ギャリックをはじめとする名優たちの演技を巡って、当時流行の「観相学」を踏まえつつ同時代的に批評した貴重な資料であるが、フットの演劇論に焦点を当てた研究はこれまでほとんどなされてこなかったためにあまり顧みられてこなかった。また、フットは『イギリス及びローマ喜劇の考察と比較』において、まだ劇作家デビュー前にもかかわらず「古典は称賛されるために読まれるが、現代作家は非難されるために存在する」と述べているが、その「現代作家」としての活動と演劇論が結びつけられて論じられることも極めて少ない現状にある。そこで本発表ではこのふたつの演劇論の分析を通じ、18世紀英国においてシェイクスピアに次ぐ2番目に多く上演されたフットの喜劇作品との関連を探りたい。特にフットの『情念に関する論文』における当時の観相学をベースにした「演技」を巡る考察と、『イギリス及びローマ喜劇の考察と比較』で照射した「演劇の現代」についての認識を彼の作品世界と結び付けることで、18世紀英国演劇の一端に新たに光を当てる機会としたい。
【プロフィール】
早稲田大学演劇博物館招聘研究員/早稲田大学エクステンションセンター講師。研究テーマはサミュエル・フット及びゴードン・クレイグの人形劇における人間/人形の身体表象分析。主な論文は「「演技」する厚紙人形たち―サミュエル・フットの人形劇『トラジェディ・ア・ラ・モード』研究」、『演劇学論集』54号(日本演劇学会 2012春)など。
新沼智之「一八世紀ドイツにおける演技理念の大転換 ― アンサンブル演技の萌芽」
【発表要旨】
18世紀半ばから後半にかけてのドイツで、俳優コンラート・エクホーフ(1720-78)は「演技」に二つの大きな大転換をもたらした。一つは、語りに重点を置いたフランス古典主義的演技から身振り・表情を重視したいわゆる自然な演技への、演技におけるアプローチの大転換である。そしていま一つは、即興的演技を克服し、文学的戯曲に基づくアンサンブル演技の確立を目指す、演技理念の大転換である。一般的な演劇史ではアンサンブル演技が確立するのは19世紀後半とされるが、その萌芽は既に遥か18世紀のエクホーフの仕事に見て取れる。彼の目指したそれは決して彼固有の取り組みで終わらず、彼の弟子や共感者たちによって引き継がれ、試行錯誤されながらもドイツ演劇の近代化のプロセスを貫く一本の線を形成しているように思われる。本発表では、エクホーフがその演技理想を実現するために、俳優をいかに統制したか、そしてまたそれがどのように継承されたかを確認して、彼の仕事をドイツにおける近代演劇確立への一つの出発点と位置づけたい。
【プロフィール】
武蔵野美術大学、明治大学、千葉商科大学で非常勤講師。研究テーマは演劇の近代化のプロセス。論文に「ドイツ演劇の近代化の出発点 ― コンラート・エクホーフの試行錯誤」『演劇の課題』(三恵社、2011)ほか。
安田比呂志
【プロフィール】
日本橋学館大学教授。専門はイギリス演劇。共著に『シェイクスピアへの架け橋』(東京大学出版会、1998)、翻訳にトマス・オトウェイ作『スカパンの悪だくみ』(『西洋比較演劇研究』第11巻、2012)などがある。

日 程:2012年7月14日(土)14:00~18:00
場 所:成城大学7号館733教室(予定)
研究発表
1 大橋裕美 小山内薫『息子』の時代―その劇作法をめぐって
要旨
小山内薫の戯曲『息子』は、大正12年(1923)3月に帝劇で初演された。その際の批評には、いくつかの注目すべき点がある。本作はハロルド・チャピン『父を探すオーガスタス』の翻案だが、多くの演劇関係者が「講釈種と見えた」「鼠小僧からヒントを得たやう」等と指摘、西洋演劇の翻案とは思えないとの感想を残した。長らく別れていた肉親と再会したものの、よんどころない事情があって名乗れない、という設定は、歌舞伎などにしばしば見られる。『息子』創作に際して、小山内は原作のほかに、瀬川如皐『与話情浮名横櫛』の一部を意識していた。翻案に見えないという批評は、小山内のこうした劇作法によるものである。その上で、登場人物3人、上演時間30分ほどの本作は、配役の成功もあり「気の利いた一作」として好評を得る。しかし一方で、父親が実の息子に最後まで気づかないことを、正宗白鳥らが甚だ不自然と批判した。親子の対面を描いた日本の諸作品と比べた場合、『息子』はこの点で非常に特徴がある。そしてそこには、数多の劇作品と一線を画そうとした小山内の意図がうかがえる。本発表は、『息子』初演の時代を考慮しつつ、同作を翻案劇として、また新作戯曲として、再評価するものである。
発表者プロフィール
明治大学兼任講師。専門は近代日本演劇。中でも翻案劇に焦点を当て、その劇作法や西洋演劇との関係性を探る。論文に「二代目市川左団次によるモリエール劇」(『西洋比較演劇研究』第9号、2010)、「『ボルクマン』後の自由劇場」(『文芸研究』第111号、2010)など。
2 譲原晶子 バレエという名の思考法
要旨
舞踊は演劇や音楽とは異なり、制作のプロセスで「実演作品」に先立ち「テクスト作品」をつくるというやり方は通常とらない。バレエでは記譜法は古くから開発されてきたが、それでも現在、譜は、完成された作品の記録のために書かれることはあっても、創作の過程でつくられることは(特定の例外を除いて)ない。しかし舞踊であっても、実演内容を認識、記憶あるいは記述し、また指示、伝達する媒体、すなわち実演について思考操作するための媒体は必要であり、バレエでその役割を担ってきたのが「バレエ用語」である。
現在使用されている「バレエ用語」を論理的に整理すると、その用法にはバレエの動きを成り立たせているしくみが示されているのが読める。本発表では、この用法が、17世紀のフイエの『コレグラフィー』においても、1980年代に独自のバレエ言語を考案したウィリアム・フォーサイスのバレエ用語においてもそのまま見られることに着眼する。17世紀からフォーサイスまでバレエの実演形態は大きな変貌を遂げてきたが、それを成立させる構成原理には不変の要素が存するということである。本発表では、バロック舞踊、クラシックバレエ、フォーサイスバレエそれぞれにおいて「用語」「実演形態」
「用語と実演形態の関係」を明らかにし、この三者を基点にバレエ史を編むことで、舞踊の構成原理からみた実演形態変遷のダイナミズムを通観する。これを通して、なぜ舞踊芸術の制作においてテクスト作品の使用は馴染まないのか、テクスと作品が舞踊で必要とされるのはどのような場合か、バレエ用語は実演形態変遷のダイナミズムにどのような役割を果たしたのかを考察したい。
発表者プロフィール
千葉商科大学政策情報学部教授。専門は西洋芸術舞踊。主な著書:Anne Woolliams: method of classical ballet, Kieser Verlag, M?nchen, 2006, 『踊る身体のディスクール』春秋社,2007。主な論文:クペcoup?からみたバレエ史,『美学』217, (2004),バレエにおけるtempsの概念,『美学』222, (2005),規範譜としてのラバン舞踊記譜法の構想とその展開,『新記号学叢書』(2005)など。

通常の例会とは異なりますが、10月の例会との関連イベントですので、ふるってご参加ください。
(7月例会については改めてお知らせいたします)
日 程:2012年7月7日(土)13:00~17:00
場 所:明治大学駿河台キャンパス1155教室(リバティタワー15階)
講師:奥香織 「18世紀パリのイタリア人劇団とその演技――「自然さ」をめぐって」
講師:大崎さやの「リッコボーニ親子の演技論について」
司会・講師:安田比呂志「情念の演技――アーロン・ヒルの造形的想像力」
講師:菊地浩平 「サミュエル・フット×ディヴィッド・ギャリック――演劇検閲法と18世紀英国の演技をめぐって」
講師:新沼智之 「18世紀ドイツにおける演技の展開――エクホーフを中心に」
本シンポジウムは、10月13日(土)に西洋比較演劇研究会で開催されるシンポジウム「18世紀ヨーロッパにおける演技の諸相」に先立ち、18世紀のフランス、イタリア、ドイツ、イギリスの各国における演技の様相を確認することを目的としています。
(本シンポジウムは、明治大学大学院文学研究科・演劇学演習ⅠAとの共催で開催されます。通常の例会とは異なり、入り口に立て看板などの案内は出ていませんので、直接教室にお越しください。)
詳細は公式サイト

場 所:成城大学7号館 733教室(予定)
1 村井華代
『水死』における大江健三郎の演劇装置
要旨
大江健三郎の小説は、しばしば歴史、あるいは個人史の再現のために演劇を「装置」として利用してきた。それは例えば、演劇として再現された過去の出来事を見た主人公が卒倒する(『万延元年のフットボール』他)、或いは村芝居が国家に抵抗する唯一の方策として上演される(『いかに木を殺すか』他)など、様々な形でおこなわれていたが、2009年の『水死』ではさらに積極的な方法が採用されている。主筋は大江本人を思わせる作家「長江古義人」の父の死の経緯を探るというものだが、全体の大半はそこに関係づけられる二つの演劇活動――長江の父の死にまつわる物語を、長江の作品と個人史から一つの劇としてまとめあげようとする劇団の企画と、村の歴史劇を現代的に再構築/解体して上演しようとする一女優の挑戦―に向けたテクスト作りと上演方法の描写に占められている。が、結局どちらの企画も上演には至らず頓挫する。
これを演劇学の立場から取り上げる理由は、『水死』が、演劇をモデルとして世界構築をおこなうテアトルム・ムンディの現代日本における一つの展開であること、そこで大江が再構築した演劇モデルは、国家的記憶と個人的記憶、その双方との関連において確定されることなく揺らぎ続けるという、演劇に対する端倪すべからざる批評に基づくこ
と、そして、演劇と、近年盛んな記憶研究がいかに関係づけられるかという見地から重要な問題を提起しているということにある。記憶そのものの劇場的性質が、記憶の物語化・舞台化という演劇実践を通じて表出するという過程の描出は、現実におこなわれる記憶/歴史の演劇化と大いに関係するであろう。
大江は作中、「演劇化」というタームを、状況に対する視点を複数化し、対話を導く場を展開する手続きという意味で使用している。このことは、統一された物語をなさない個人の記憶や国家の歴史が、舞台化を機に肉体化/可視化され、確定されてゆくプロセスとどう関係づけられるだろうか。20世紀のトラウマと向き合い続ける日本の作家が仕掛けた「装置」から、演劇と記憶/歴史の関係を考えたい。
発表者プロフィール:愛媛県出身。明治大学文学研究科演劇学博士後期課程満期退学。早稲田大学演劇博物館21世紀COE演劇研究センター助手(西洋演劇)を経て、現在共立女子大学文芸学部准教授(劇芸術コース)。時代・国別を特化せず西洋演劇理論全般を扱う。最近の関心領域は反演劇主義思想とユダヤ‐キリスト教思想の関係等。

翻案戯曲『ジークフリート』と1928年――挑戦と逆行と
要旨
1928年は、ベケットがジョイスに出会い、ブルトンが『ナジャ』を発表、ベルリンでは『三文オペラ』が初演された。そして、ジャン・ジロドゥが『ジークフリート』の華々しい成功とともに劇界にデビューした年でもある。これは1922年に発表した長編小説『ジークフリートとリムーザン人』を作家自ら翻案したものである。
演劇が夢のジャンルだった19世紀後半を経て20世紀に入ると、小説は独自の地位を確立する。プルーストのように、演劇に親しみつつも、戯曲というジャンルに求められる語りの形式の束縛を好まず自らは劇作への転進を試みない小説家も増えた。劇界では「カルテル」の4人の演出家たちが新たな書き手を積極的に探し求めていた一方、依然商業演劇が人気を博していた。ジロドゥは、劇界の求めにこたえて、あえて戯曲というジャンルの束縛を選びとった小説家であるといえる。
小説の語りは、演劇の語りにどのように移し得るか、あるいは移し得ないかについては、拙著ですでに考察を試みているが、今回の発表では、この小説の翻案の問題を、1928年の演劇史の文脈において捉えなおしてみたい。1928年に、戯曲というジャンルの束縛をあえて選びとるということは、いったいどういうことなのか。翻案にあたり、作家がすでに持っていた何が犠牲にされ、いまだ持っていなかった何がどこから持ち込まれ接木されたのか。ジロドゥによる翻案の実例の分析と、時代背景や当時の劇界等の人的交流のありようを連関させ、それを切り口として、1928年のフランスを立ち上がらせたい。
発表者プロフィール:2010年より早稲田大学文學学術院助教。研究分野はフランス近現代演劇ならびにフランス語教授法。両大戦間期のフランス出版界ならびに劇界における「絵描き」の仕事をめぐる人的交流を調査・研究中。著書に、『小説から演劇へ ジャン・ジロドゥ 話法の変遷』(早稲田大学出版部、2010年)、「寺山修司におけるジャン・ジロドゥからの影響――ラジオドラマ『大礼服』論」『演劇学論集』54号(日本演劇学会、2012年春)などがある。